日本語教師の講座選びなら
BrushUP学び

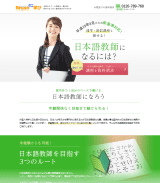

BrushUP学びは日本語教師養成講座や日本語教育能力検定試験の対策講座など、日本語教師を目指せるスクールの情報をまとめたサイトです。エリア別にまとめて比較でき、とても見やすいです。


この記事を書いたのは
Miku
日本語教師養成課程で資格を取得し、日本語の指導歴は7年目。
学生時代はイギリスへの交換留学の経験もあり、卒業後は日本語教師として働きながら、フランスでワーキングホリデー留学と語学留学を経験。
現在はマルタ島在住で主にフリーランスで活動する傍ら、「日本語教師ナビ」のライターを務める。
日本語教師の国家資格・登録日本語教員を取得するために必要な「日本語教員試験」は、2024年(令和6年)11月17日に、初めて実施されました。
しかしながら、基礎試験・応用試験の両方を受けた受験者の合格率は、9.3%という結果になっており、特に基礎試験の難易度の高さが指摘されています。
また、現時点で過去問が公開されていないため、試験対策をしにくいと感じる方が多いようです。
そこで今回は、NPO法人の国際教育振興協会・日本語教師ネットワーク機構で、代表理事を務める新城宏治さんからいただいたコメントを紹介しながら、日本語教員試験の対策方法についてまとめます。
日本語教員試験の出題内容は、予告なしに変更されることがあるため、本記事は参考程度にご覧ください。
参考:文部科学省「令和7年度 日本語教員試験 試験案内」、「令和6年度日本語教員試験実施結果について」
\\日本語教員試験の合格率を上げるなら//
スポットで受講できる
日本語教員試験対策講座はこちら
\\日本語教員試験の合格率を上げるなら//
スポットで受講できる
日本語教員試験対策講座はこちら
前述したように、日本語教員試験というのは、2024年度から始まった日本語教師の国家資格(登録日本語教員)の資格を取得する上で、受験が必要となる試験です(現職者で経過措置を活用する場合は免除される場合もあります)。
この試験は、基礎試験と応用試験から成り立っており、基礎試験の合格者は、登録実践研修機関で実施される実践研修を受講できます。
また、登録日本語教員の資格を取得する方法には、日本語教員試験(基礎・応用の両方)に合格して、実践研修を修了する「試験ルート」と、登録日本語教員養成機関で課程を修了して、日本語教員試験(基礎試験は免除)に合格し、実践研修を修了する「養成機関ルート」があります。
関連記事:登録日本語教員の試験(日本語教員試験)とは?、【2024年施行】登録日本語教員とは?、登録日本語教員の資格取得ルートにはどのようなものがある?、登録日本語教員養成機関と登録実践研修機関とは?
\\日本語教員試験の合格率を上げるなら//
スポットで受講できる
日本語教員試験対策講座はこちら
日本語教員試験の基礎試験は、日本語教育を行う上で、必要となる基礎的な知識・技能がどの程度あるかを測るものです。
基礎試験の概要は、以下の通りです。
基礎試験は、大問が18問あり、4つの選択肢から回答を選んでいきます。
| 試験時間 | 120分 |
| 出題数 | 100問(1問1点) |
| 出題形式 | 選択式 |
| 出題割合(区分ごと) | 社会・文化・地域:約1〜2割 言語と社会:約1割 言語と心理:約1割 言語と教育(教育実習を除く):約3〜4割 言語:約3割 |
| 合格基準 | 必須の教育内容5区分において、各区分で6割以上かつ総合得点で8割以上の得点が必要 |
基礎試験に合格するための対策方法は、以下のようなものがあります。
関連記事:必須の教育内容50項目とは?

新城宏治さん
2025年度の日本語教員試験は11月2日(日)に行われます。
日本語教員試験は複数のルートがあるため、基礎試験から受験する人と、応用試験から受験する人では、おのずと準備すべきことは違ってきます。
基礎試験から受験する人は、まずは基礎試験に合格することが大切です。
なぜなら、基礎試験に合格しなければ応用試験は採点外となってしまうからです。
また、2024年度の試験結果を見る限り、基礎試験に合格した人のほぼ100%が応用試験にも合格していますので、基礎試験に合格する力があれば、応用試験にも合格できる可能性が高いです。
基礎試験に合格するには、5区分の各区分で6割程度、全体で8割程度の得点が必要です。
そのためには、苦手な区分をなくすこと、教科書に書いてあることは「すべて理解する」ことが必要です。
8割というハードルは高く、そのぐらい完全にカバーしていなければ取れる点数ではありません。
逆にそのぐらい完璧にしておけば、応用試験の読解にも自信を持って取り組めます。
以下に、日本語教員試験の基礎試験と、日本語教育能力検定試験・試験Ⅰの比較表を作成してみました。
| 日本語教員試験・基礎試験 | 日本語教育能力検定試験・試験Ⅰ | ||||
| 試験時間 | 出題数 | 出題形式 | 試験時間 | 出題数 | 出題形式 |
| 120分 | 100問 | 選択式 (4択のみ) |
90分 | 100問 | 選択式 (4択もしくは5択) |
このように、日本語教員試験・基礎試験の方が、1問にかけられる時間が長くなり、5択問題がなくなったことから、日本語教育能力検定試験・試験Ⅰよりも簡単になったと感じる受験者が多いようです。
\\日本語教員試験の合格率を上げるなら//
スポットで受講できる
日本語教員試験対策講座はこちら
日本語教員試験の応用試験は、日本語教育に関する基礎的な知識・技能を活用した問題解決能力を測るもので、読解試験と聴解試験に分かれています。
応用試験(読解)の概要は、以下の通りです。
こちらの試験は、長い文章を読んで4つの選択肢から回答を選ぶ形式となっています。
| 試験時間 | 100分 |
| 出題数 | 60問(1問1点) |
| 出題形式 | 選択式 |
| 合格基準 | 読解と聴解の総合得点で、6割以上の得点が必要 |
応用試験合格に向けて、読解問題で点数を取るための対策方法には、以下のようなものがあります。
以下の表は、応用試験(読解)と日本語教育能力検定試験・試験Ⅲを比較したものです。
| 日本語教員試験・応用試験(聴解) | 日本語教育能力検定試験・試験Ⅲ | ||||
| 試験時間 | 出題数 | 出題形式 | 試験時間 | 出題数 | 出題形式 |
| 100分 | 60問 | 選択式 | 120分 | 80問+記述 | 選択式 記述式 |
応用試験の読解問題では、日本語教員試験の方が問題数も時間も少なくなっている上に、記述問題がないため、日本語教育能力検定試験より余裕を持って試験に臨めると感じている方が多いようです。
\\日本語教員試験の合格率を上げるなら//
スポットで受講できる
日本語教員試験対策講座はこちら
日本語教員試験の応用試験で、読解問題とともに出題される聴解問題の概要を、以下にまとめます。
聴解問題で流れる音声は1度のみで、4つの選択肢から回答を選びます。
3つの大問から成り立っており、大問1は学習者の発話を聞いて、問題点を指摘するもの、大問2は日本語の母語話者(教師など)と、非母語話者の会話を聞いて質問に答えるもの、大問3は聴解教材についての問いに答えるものとなっています。
| 試験時間 | 50分 |
| 出題数 | 50問(1問1点) |
| 出題形式 | 選択式 |
| 合格基準 | 前述の通り、読解と聴解の総合得点で、6割以上の得点が必要 |
応用試験の聴解問題は、音声が1回しか流れないということもあり、以下のような戦略的な対策をする必要があります。

新城宏治さん
応用試験から受験する人は、まずは聴解試験の対策を進めることをおすすめします。
なぜなら、聴解試験は対策をすればするほど、得点が上がりやすいからです。
日本語教員試験の聴解試験対策の問題集は、まだあまり出版されていませんが、日本語教育能力検定試験の過去問などを利用しながら、対策をするのがいいでしょう。
応用試験(聴解)と、日本語教育能力検定試験・試験Ⅱを以下で比較してみました。
| 日本語教員試験・応用試験(聴解) | 日本語教育能力検定試験・試験Ⅱ | ||||
| 試験時間 | 出題数 | 出題形式 | 試験時間 | 出題数 | 出題形式 |
| 50分 | 50問 | 選択式 | 30分 | 40問 | 選択式 |
日本語教員試験の聴解問題では、問題数が多く、時間も長いため、より高い集中力・情報処理能力が求められるようになりました。
\\日本語教員試験の合格率を上げるなら//
スポットで受講できる
日本語教員試験対策講座はこちら

新城宏治さん
基礎試験も応用試験も、問題演習を通してたくさんの問題に当たるようにしましょう。
本を読んだだけでは、もしかすると「分かったつもり」になっているかもしれません。
問題に当たることで、自分は何が分かっていて何が分かっていないのか、これから何に取り組めばいいのかが具体的に見えてきます。
皆さんのご健闘をお祈りしています。
\\日本語教員試験の合格率を上げるなら//
スポットで受講できる
日本語教員試験対策講座はこちら
日本語教員試験の範囲は、「登録日本語教員実践研修・養成課程コアカリキュラム」に記載されている必須の教育内容となっています。
したがって、試験範囲の内容はかなりボリュームがあり、独学で試験への合格を目指すことは可能ですが、効率よく学習を進めたいという方には、養成課程が実施する対策講座の受講がおすすめです。
対策講座では、以下のような内容を学ぶことが可能です。
養成課程によって、カリキュラムが異なるため、詳細は各機関へお問い合わせください。
\\日本語教員試験の合格率を上げるなら//
スポットで受講できる
日本語教員試験対策講座はこちら
日本語教員試験の対策講座でおすすめの養成機関は、以下の通りです。
| 養成機関名 | 特徴 |
| KEC日本語学院 | 30時間・60時間・90時間コースから選べる |
| 資格スクール大栄 | スキマ時間を活用して学べる |
| カナン東京日本語教師養成講座 | 通学orオンラインの好きな方で学べる |
| ECC日本語学院 名古屋校 | 応用試験の対策講座のみを開講 |
| ルネサンス日本語学院 | オンライン完結型。視聴期間は2年間 |
| アガルートアカデミー | 出題範囲の重要ポイントを効率よく学習可能 |
| アークアカデミー | e-ラーニングなど、オリジナル教材が充実 |
\\日本語教員試験の合格率を上げるなら//
スポットで受講できる
日本語教員試験対策講座はこちら
今回は、日本語教員試験の対策方法について、新城宏治さんからいただいたコメントを紹介しながら、解説しました。
日本語教員試験は、まだ1回しか実施されておらず、過去問も公開されていないので、対策がしにくいと感じている人が多いかもしれません。
これから試験を受験する方は、新城さんからアドバイスをいただいたように、基礎試験では苦手分野をなくすこと、参考書の内容はすべて理解することを意識して、学習を進めてみましょう。
また、応用試験では聴解試験に力を入れて取り組むと、点数を上げられるかもしれません。
試験対策を効率よく進めたいという方は、養成機関が提供している対策講座の受講を検討してみてはいかがでしょうか。
\\日本語教員試験の合格率を上げるなら//
スポットで受講できる
日本語教員試験対策講座はこちら
今回日本語教員試験に関するアドバイスをいただいた新城宏治さんが代表理事を務められているNPO法人国際教育振興協会 日本語教師ネットワーク機構は、日本語を必要とする全ての外国人に適切な日本語教育を提供するために、日本語教師や日本語教育に関する情報を様々な形で発信しているNPO法人です。
関連記事:新城宏治さんにインタビュー!日本語教育を通して共生社会の実現に貢献したい
\\日本語教員試験の合格率を上げるなら//
スポットで受講できる
日本語教員試験対策講座はこちら

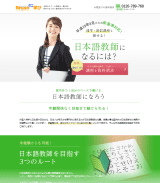

BrushUP学びは日本語教師養成講座や日本語教育能力検定試験の対策講座など、日本語教師を目指せるスクールの情報をまとめたサイトです。エリア別にまとめて比較でき、とても見やすいです。